「住宅ローンの返済が困難で任意売却を検討しているけれど、本当に売却できるのか」
「任意売却に失敗したらどうなるのか」
任意売却を検討している方の中には、このような悩みを持っているケースも多いでしょう。
今回はそのような方に向けて、任意売却ができないケースや成功のための対策を解説します。競売を回避するために知っておくべきポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
任意売却とは?──競売との違いと、知っておきたい基本
任意売却とは、住宅ローンが残っている不動産を債権者(金融機関)の許可を得て売却する方法です。
売却価格より残債が多い「オーバーローン状態」でも、任意売却を利用すれば売却することができます。
任意売却に近い売却方法で「競売」という方法があります。競売とは、債権者が裁判所に申し立てて不動産を強制的に売却する手続きのことです。任意売却による処分が難しい場合に競売に移行する流れが一般的です。
任意売却は債権者と債務者(売主)の合意によって売却価格が決まる一方で、競売は裁判所の手続きにより売却価格が決まります。さらに、任意売却は市場価格に近い価格で売却できるのに対し、競売では5割〜7割程度になる点も違いの1つです。
任意売却が「売却不可」となる3つの主要因
ここからは、任意売却できないケースを理由とともに解説します。
任意売却ができないのは、債権者との交渉の難しさや価格と債務のバランス、物件や権利の複雑さが要因として挙げられます。
1,債権者との交渉が不調に終わるケース

まずは、債権者との交渉が不調に終わることにより任意売却できないケースを見ていきましょう。
複数債権者との調整が難しい理由
複数の債権者との調整が難しいのは、債権者それぞれの利害が対立するためです。住宅ローン以外に別の金融機関が後順位の抵当権(優先順位が低い抵当権)を設定している場合、売却代金の配分で調整が必要になります。
後順位の債権者(優先順位が低い抵当権を設定した金融機関)は第一抵当権者(最も優先順位の高い抵当権を設定した金融機関)がお金を回収したあとの残額を限度にしか回収できないため、配分の調整が難しい傾向にあります。さらに、税金の滞納による差押えがある場合は、自治体への配分も考慮しなければなりません。
このように、限られた売却代金を複数の債権者がなるべく多く回収しようとするため、配分の調整が難しくなり、任意売却の交渉が不調に終わることがあります。
債権者の提示条件が厳しすぎる場合
債権者の提示条件が厳しすぎることも、任意売却が不調に終わる要因です。
金融機関の中には、売却最低価格を市場相場より高く設定したり、売却代金からの配分割合を高めに要求したりするケースがあります。また、引越し費用や仲介手数料の配分を認めないなどの、厳しい条件を提示されることも考えられるでしょう。
債権者の提示条件が厳しすぎると債務者との合意が難しいため、交渉が不調に終わってしまいます。
2,売却価格と債務残高のギャップが大きいケース

次に、売却価格と債務残高(住宅ローン残高)のバランスが合っていないケースを紹介します。
相場を大きく下回る査定額
相場よりも大きく下回る査定額が出た場合、任意売却が難しくなります。
査定額が相場を下回る要因としては、以下が考えられます。
- 建物の老朽化が進んでいる
- 立地条件が悪い
- 瑕疵物件に該当する
建物の老朽化により雨漏りや傾きなどがあると、相場よりも売却価格が下回りやすくなります。さらに、交通アクセスや利便性が極端に悪いことも売却価格が低くなる要因です。
不動産の取引において、物理的・法律的・心理的な欠陥がある「瑕疵物件」に該当する場合も、相場を大きく下回る恐れがあります。
債権者が納得しない売却条件
債権者が納得しない売却条件では、任意売却は成立しません。売却価格が債権者の期待を下回る場合や、売却に伴う配分に合意が得られないケースが考えられます。
債権者はなるべく多くの金額を回収したいと考えているものの、不動産の立地や状態によって希望する価格では購入希望者がつかないことも少なくありません。例えば、市場価格が1,500万円にもかかわらず、債権者が1,800万円以上での売却を条件とした場合、購入希望者が見つからず任意売却が不調に終わる恐れがあります。
さらに、債権者が売却代金から引越し費用や測量費用などの必要経費を差し引くことに反対するケースもあり、債権者の合意が得られない場合は任意売却ができなくなります。
3,複雑な物件や所有権の問題が絡むケース
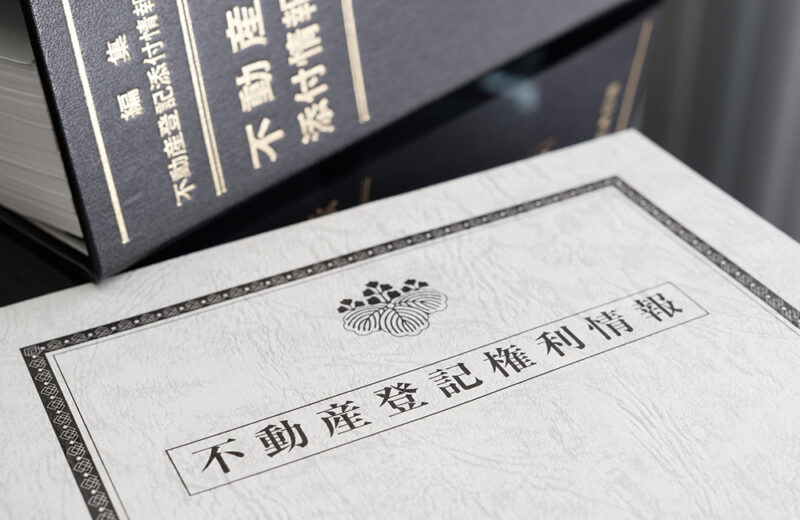
最後は、複雑な物件や所有権の問題が絡むケースです。複雑な権利関係や物理的な問題も任意売却が不調に終わる原因となります。
共有名義や抵当権設定のトラブル
任意売却が難しくなる要因として、共有名義や抵当権設定のトラブルが挙げられます。
共有名義の場合、共有者全員の同意がなければ売却できません。例えば、離婚した元配偶者が共有者となっているケースでは、連絡が取れず同意を得られないことがあります。
さらに、相続により複数の相続人が共有者となっている場合、意見がまとまらず手続きが進まないケースも考えられるでしょう。
また、複数の金融機関が抵当権を設定している場合、各債権者からの同意を取得しなければならないため、調整が難しくなる傾向にあります。このように、権利関係が複雑化することで、任意売却が難しくなるのです。
物理的な問題(土地境界線の不明瞭など)
物件に物理的な問題がある場合も、任意売却が難しくなります。物理的な問題があると売却価格が相場よりも低くなるため、債権者の同意を得るのが難しくなるのです。
不動産取引における「物理的な問題」には、主に以下が挙げられます。
- 土地境界線が不明瞭である
- 接道義務を満たしていない
- 建物に建築基準法違反の増築部分がある
境界線が不明瞭な土地は購入希望者が不安を感じやすくなり、売却価格が相場よりも低くなるケースがあります。また、接道義務を満たさない土地や建築基準法違反の増築部分がある建物は、購入希望者が住宅ローンを利用できないため、売却価格が下落する要因となります。
競売を避けるための3つのポイントと行動ステップ

ここでは、競売を回避し任意売却を成功させるためのポイントや知識、準備について解説します。
①任意売却の「期限」を理解する
任意売却には期限があります。
スケジュールやタイムリミットをあらかじめ把握しておけば、任意売却の失敗を防げるでしょう。
競売開始決定までのタイムリミット
競売の開始が決定するまでのタイムリミットは、住宅ローンの滞納から半年〜1年程度が一般的です。そして、競売を回避できる最後のチャンスは、競売の開札(結果発表)期日の前日です。
通常、滞納から3ヶ月〜6ヶ月で期限の利益が喪失(住宅ローンを分割で返済する権利を失うこと)し、債権者が裁判所へ競売の申し立てを行います。申し立て後、裁判所による現況調査や評価書作成を経て競売開始が決定され、入札が開始されるという流れです。
任意売却を成功させるためには、競売開始決定までのタイムリミットを把握し、なるべく早く動き出すことが重要です。
早期相談が成功の鍵となる理由
競売を避けるためには、金融機関や不動産会社へ早めに相談しましょう。その理由は、準備期間を確保し、選択肢の幅を広げるためです。
「滞納するかもしれない」と思った時点で相談することで、住宅ローンの条件変更の相談や通常の売却など、任意売却以外の解決策も検討できます。
さらに、早めに相談することにより、共有名義人との調整時間を十分に確保できます。
離婚した元配偶者や遠方の親族との連絡調整には時間がかかるため、余裕をもった準備が必要です。また、物件の査定や市場調査を複数の不動産会社に依頼し、最適な販売戦略を立てることも可能になります。
②信頼できる不動産会社・専門家の選び方
任意売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社や専門家を選ぶことが大切です。
信頼できる不動産はどのように見抜けば良いのでしょうか。
任意売却の実績をどう見抜くか?
信頼できる不動産を見抜くためには、任意売却の実績が豊富かどうかを見極めましょう。
実績が豊富な不動産会社は、金融機関や保証会社との交渉ノウハウを蓄積しているため、有利な条件での売却が期待できます。任意売却の実績は、ホームページを確認したり、担当者へ直接質問したりすれば答えてくれます。特に、年間の任意売却取扱件数や平均売却期間などの数値データを公開している会社は信頼性が高いといえます。
また、ホームページに具体的な解決事例や顧客の声を掲載している会社も実績の裏付けとなるでしょう。
専門家との連携で交渉をスムーズに進める
債権者との交渉をスムーズに進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家と提携している不動産会社を選びましょう。
専門家と連携している不動産会社を選べば、任意売却後の残債処理や債務整理まで見据えた総合的なサポートが受けられます。例えば、法律の専門家と連携している不動産会社に依頼した場合、債権者との交渉において法的根拠に基づいた提案をしてもらえます。
さらに、任意売却後の生活再建まで含めたトータルプランも提示してくれるため、依頼者の不安軽減にもつながるでしょう。
③任意売却を成功に導くための必要書類と準備
ここでは、任意売却に必要な準備や心構えについて解説します。
査定に必要な書類リスト
任意売却では、売却価格を決めるために査定をおこないます。
査定に必要な主な書類は次のとおりです。
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 住宅ローンの返済予定表
- 物件の図面
- 管理費や修繕積立金がわかる書類(分譲マンションの場合)
- 権利証
- 免許証などの身分証明書
登記簿謄本で所有者や抵当権の設定状況、土地面積や延床面積などを確認し、固定資産税評価証明書で公的な評価額を把握します。住宅ローンの返済予定表からは、残っている住宅ローンの金額がわかります。
物件の図面で概要を把握し、分譲マンションの場合は管理費や修繕積立金、ガレージ代などがわかる書類を用意しましょう。本人確認のための身分証明書や、不動産の所有者である証明として権利証も忘れずに準備してください。
これらの書類を忘れずに用意すれば、スムーズに査定を進めることができるでしょう。
債権者への「お願い」ではなく「提案」を
好条件で任意売却を成功させるためには、債権者の「お願い」ではなく「提案」を心がけましょう。感情的に懇願するのではなく、客観的なデータに基づいた提案が重要です。
客観的なデータとは、以下のようなものを指します。
- 市場価格の調査結果
- 競売予想価格との比較
- 売却スケジュール
- 配分案の詳細
不動産会社が上記のデータを用意してくれることもありますが、所有者本人もきちんと把握しておく必要があります。債権者が判断しやすい形でデータを示し、感情論ではなくビジネス的な交渉として任意売却を進めましょう。
【もしもに備える】「売却不可」となった後の選択肢と心構え

任意売却が失敗に終わっても、人生が終わるわけではありません。
競売を十分に理解し、競売後に残る債務ときちんと向き合えば、良い形で再出発できるでしょう。
競売への移行は本当に最悪のシナリオか?
結論、任意売却が失敗して競売に移行することは、最悪のシナリオではありません。
競売の特徴を知り、前向きに捉えることで希望が見えてくるでしょう。
競売のメリット・デメリットを冷静に比較する
競売のメリット・デメリットを冷静に比較すれば、競売が必ずしも最悪の選択肢ではないことがわかります。
競売のデメリットとしては売却価格が低くなり、残債が多く残る点が挙げられます。また、任意売却とは違い、売却代金から引越費用を出してもらえないため、自腹で引っ越さなくてはいけません。
一方で、競売は家の売却手続きをすべて裁判所と債権者がおこなうため、債務者にとって手間がかからないメリットがあります。また、売却代金の配分も裁判所が決定するため、債権者間の調整で悩む必要がありません。
このように、競売のデメリットばかりに目を向けるのではなく、生活を立て直すための時間が取れるというメリットにも注目してみましょう。
精神的な負担を軽減するための考え方
精神的な負担を軽減するための考え方は、競売を「失敗」ではなく「再出発の機会」として捉えることです。
住宅を失うショックは大きいですが、将来への希望は失われていません。競売により住宅ローンの重圧から解放されれば、収入を生活費や将来への投資に充てられます。賃貸住宅へ引っ越せば、固定資産税や修繕費の負担がなくなり、家計が身軽になる可能性も考えられるでしょう。
また、不利な信用情報は5年〜10年程度で回復することが多く、その後は住宅ローンを組むことも可能です。競売で一時的な住環境の変化はあっても、経済的な安定を取り戻すことで精神的な余裕が生まれるでしょう。
競売後も残る債務への向き合い方
競売をおこなった後も債務は残りますが、債務と真摯に向き合えば、良い形で再出発できます。
ここで紹介する生活再建プランを参考に、競売後の生活を考えてみてください。
残債処理の交渉と生活再建プラン
競売後の返済額は、債務者の収入状況に応じて月5千円〜3万円程度の分割返済が認められるケースが一般的です。債権者との交渉では、家計収支表を作成し、生活に必要な最低限の費用を差し引いた金額での返済を提案しましょう。
無理な返済計画は継続できないため、現実的な金額設定が重要です。また、ボーナス時の増額返済や、将来的な一括返済の可能性も含めて提案すれば、債権者の理解が得やすくなります。
例えば、月の手取り額が30万円の場合、以下の生活再建プランが考えられます。
- 生活費:20万円
- 残債返済:2万円
- 貯蓄:3万円
- 予備費:5万円
5年間で120万円貯蓄し、将来的に住宅購入の頭金とすることで、現実的な将来設計が描けます。具体的な数値で計画を立てて、前向きに再出発を目指しましょう。
まとめ:任意売却の成功は「知識」と「行動」が鍵になる

今回は、任意売却ができないケースをテーマに、任意売却ができない3つの主な要因と競売を避けるための対策を解説しました。
任意売却の成功は「知ること」と「行動すること」の2つが鍵です。期限やリスクを正しく知り、早めの相談と周到な準備をおこなえば、任意売却の成功率が向上するでしょう。さらに、専門性の高い不動産会社や法律の専門家に相談することで、好条件での売却が可能です。
この記事で解説した内容を参考にして、任意売却を成功へ導きましょう。







